
水位検知AI開発事例を紹介
このページでは、水位検知AIの開発事例を紹介します。どのような業界で、どんな目的で導入されているのか、得られた成果などもまとめています。
AI開発の依頼・ツール導入を検討している方は、参考にしてください。
アーベルソフト(IT)

導入前の課題:
自社開発モデルの運用負担と精度向上の限界
アーベルソフトは、災害時の視覚情報を活用した防災DXサービス「ビューちゃんねる」を複数の自治体に提供している企業です。
自社で開発した画像認識モデルにより、冠水の有無を自動で判定するWebサービスも展開してきました。
しかし、災害時の画像データが少ない上、モデルの精度を上げるための専門知識が不足しているなど、機械学習モデルの開発・運用にはさまざまな課題がありました。
導入後の成果:
生成AIの活用で精度向上と
工数削減
生成AIの導入を検討し、最終的にAmazon Bedrockを採用。導入初期は、生成AIが誤検知を起こす場面も多く見られましたが、IPカメラごとの画角や写り込むオブジェクトを考慮。
状況判断に必要な要素のみを抽出するプロンプトを工夫したことで、判定精度が改善されました。
AIの出力は文章ではなく、JSON形式でスコア化された数値を返すように設計し、冠水の傾向をより精緻に把握できるようにしています。
鳥取県(地方自治体)

導入前の課題:
現地確認だけでは
間に合わない監視体制
鳥取県では、局地的豪雨による農業用ため池の決壊リスクが高まっており、早期の情報把握が求められていました。
しかし、従来の監視体制は現地に出向いて目視確認を行う方法が中心。災害発生時に現地到達が遅れる、状況把握や避難判断の初動が遅い、などさまざまな課題を抱えていました。
また、情報の共有体制も整っておらず、管理者と防災部局、下流住民の間で連携が取りづらい状況が続いていました。
導入後の成果:
遠隔監視で初動が加速
鳥取県は「ため池監視システム導入推進事業」を通じて、三信電機のため池管理システムを採用。現地に水位センサーや監視カメラを設置し、即時にデータを取得できるようにしました。
管理者はWeb上で水位の変化や現場画像をリアルタイムに確認できるため、異常時の判断が迅速に行えます。
自治体防災部局や住民との情報共有も可能になり、地域全体での連携が強化。リアルタイムな遠隔監視が実現されたことで、現地確認の負担が軽減され判断スピードが向上しています。
静岡県(地方自治体)

導入前の課題:
映像監視と目視確認に頼る
運用
静岡県内のある自治体では、これまで河川の氾濫対策として、水位センサーと監視カメラを併用した運用を行っていました。
しかし、実際の運用では暴風や豪雨といった悪天候下では映像の視認性が低く、正確な状況把握が困難。結局、最終的な判断をするため職員が現地へ出向き、目視で確認せざるを得ない状況でした。
人的な負担と危険を伴うこのような対応は大きな問題です。緊急時に迅速な意思決定ができないだけでなく、職員の安全も脅かされていたからです。
導入後の成果:
AIによる即時検知と自動発報で災害対応を強化
そこで、カメラ映像をリアルタイムで解析し、水位の上昇を自動で検知・発報するAI映像解析ソリューション「TRASCOPE-AI」を導入。大雨による警戒水位到達時に即時にアラートが発報されるため、的確な判断ができるようになりました。
映像解析から得られるデータによって、風雨による視界不良の中でも判断ができるように。現場へ職員を派遣することもなくなり、災害時のリスク回避にも大きく貢献しています。
水位検知AIを開発する方法
映像解析プラットフォームを活用
映像解析プラットフォームを利用し、カメラ画像にデジタルの目盛り(仮想量水標識)を設置して水位を検知するという方法が考えられます。この方法では物理的な水位計を設置する必要がなく、画面の情報からAIが読み取りを行い水位の数値化が可能となります。ゼロから開発を行うよりも開発期間を短くすることができる点がメリットといえますが、カメラの設置工事や夜間や悪天候においても正確な計測が可能になるような調整は難易度が高いことから、専門的なベンダーに相談することがおすすめといえます。
クラウドAIサービスを利用し量水標の読み取りを行う
AWSなどの汎用AIを利用することによって、川に設置された量水標の数値を読み取るAIを開発するという方法も考えられます。この方法の場合、文字・物体を認識するAIに対して水位計の画像を学習させることによって、「現在水面はどの数字のところにあるのか」という判定を行えるようにします。既存の量水標をそのまま活用できる点、AIモデルの作成はクラウド上の操作で完結できるといったメリットがあるものの、雨や泥などで量水標の目盛りが汚れた場合の補正処理や警報システムとの連携などが必要になってくる場合には、システム開発会社へ相談・委託することが推奨されます。
セグメンテーション技術を用いて水面領域を解析
「PyTorch(パイトーチ)」などのフレームワークを使用することによって、「水の部分」「陸の部分」をピクセル単位でラベル付けするAIを独自に開発するという方法も考えられます(セグメンテーション)。例えば水位計がない場所、氾濫が発生してどこが川なのかわからないといった場合にも、画面中でどれくらいの割合が水で埋まっているのかを解析することにより浸水状況の把握につなげます。ただ水面は常に見た目が変化することから、高い精度での認識を実現するには高度な知識が必要となります。
画像解析AI開発ツール・プラットフォームの料金・機能比較
ここでは、クラウドやオンプレミスなどのタイプ、料金、主な対応業界などの詳細情報を公式HPに掲載している画像解析AI開発ツール・プラットフォームをピックアップして比較します。
| Bind Vision (キヤノンITソリューションズ) 
引用元:キヤノンITソリューションズ公式HP (https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/cross-industry/image-integration/bindvision/brand) |
OPTiM AI Camera Enterprise (OPTiM) 
引用元:OPTiM AI Cameraシリーズ公式HP (https://www.optim.co.jp/optim-ai-camera/) |
オールインワン AI画像解析パッケージ (大塚商会) 
引用元:大塚商会公式HP (https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/ai-iot/ai-camera-analysis/) |
|
|---|---|---|---|
| タイプ | クラウド | オンプレミス/クラウド (選択可) | オンプレミス |
| 基本料金 |
|
|
|
| 導入までの期間 | 即時 (契約後すぐに使用可能) | 最短約6週間 | ― (公式HPに記載なし) |
| トライアル | 有り (1か月無償で使用可能) | ― (公式HPに記載なし) | ― (公式HPに記載なし) |
| API | Web APIでプログラムを 問わず、連携可能 ※2 | APIで既存アプリ、 システムとの連携が可能 | ― (公式HPに記載なし) |
| 主な対応業界 | 製造業/防災事業者/自治体 | 小売業/交通機関/医療業界 | 建設業/小売業/製造業 |
「画像解析AI開発ツール」とGoogle検索して上位表示されるAI開発ツール30社のうち、クラウドorオンプレミスでのプラットフォームを提供している製品をピックアップし、
公式HPに導入費用などの価格掲載があるソフトの情報を掲載しています。
※1.OPTim Edge Entryの場合、カメラ5台まで処理可能。
※2.煙検出AIの場合、1セット=45,000回/月の実行回数。
(2025年3月5日調査時点)
水位検知AIは、IT企業による技術革新や自治体の防災対応力向上を背景に、さまざまな分野で導入が進んでいます。しかし目的や現場環境によって導入手法や工夫すべきポイントは大きく異なります。
AIを効果的に活用するためには、汎用的な技術をそのまま当てはめるのではなく、「業界ごと」「現場ごと」に異なる課題や運用上の制約を丁寧に洗い出すことが重要です。AIの導入や開発は、自社・自組織のニーズに応じた活用を検討しましょう。
また、当メディアではシステム開発の業界・目的別におすすめの画像解析AIを紹介しています。製造業、医業、金融業など、開発システムを活用する業界・目的によって、選ぶべき画像解析AIは変わってくるもの。自社の開発システムに合った画像解析AIを導入したいと考えているSIer・AI事業者の皆様は参考にしてみてください。
各製品・サービスをじっくり比較・検討したい方のために、画像解析AIを利用できる開発ツール・ソリューションを一覧掲載しているページもご用意しています。機能や料金の違いを知りたい方は、こちらも併せてご確認ください。
画像解析AIのおすすめ3選
様々な画像解析AIのなかで、DX化実現のため大規模なシステム構築が求められる製造業、高度な解析精度が医療業界、セキュリティが重視される金融業界と3つの業界で目的に合うツールをピックアップしました。
確立したい
Bind Vision
(キヤノンITソリューションズ)

https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/cross-industry/image-integration/bindvision/brand
- 拡張性の高いプラットフォームで、用途・ライン別の分割運用、全体の統合管理が可能。カメラの増設にも柔軟に対応
- 製造ラインの状況を一画面で俯瞰し、アラート通知で異常を即時検知。Web APIでスムーズなシステム連携を実現
解析したい
Aivia
(ライカマイクロシステムズ)
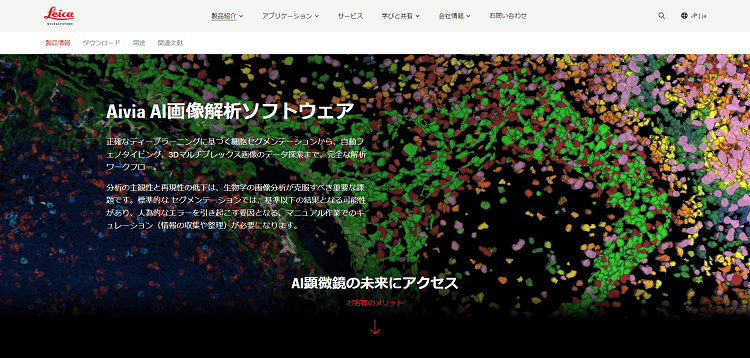
https://www.leica-microsystems.com/jp/製品紹介/画像解析システム/p/aivia/
- 生体組織に求められる2D~5Dの可視化と解析を実現。神経細胞や臓器構造の観察にも対応できる
- 45種類以上の顕微鏡画像ファイルフォーマットに対応。様々な用途の研究用データなども無駄なく活用
重視したい
Azure AI Vision
(日本マイクロソフト)

https://azure.microsoft.com/ja-jp/products/ai-services/ai-vision
- Microsoftの高度なセキュリティ基準に基づいて設計。クラウド経由の取引にも対応が可能
- 金融・保険の書類処理や自動データ抽出するOCR、オンライン本人確認機能を搭載。口座開設や本人確認業務を効率化