
画像解析AIアルゴリズムを解説
ここでは、画像解析AIシステムの開発で利用される画像認識のAIアルゴリズムについて解説しています。種類別の特徴のほか、選び方や実装のポイントもまとめているので、画像解析AIシステム開発を進めたいSIer・AI事業者の皆様は参考にしてみてください。
画像解析AIアルゴリズムとは?
画像解析AIアルゴリズムとは、コンピューターが画像データを理解し、特定のタスクを実行するための計算手法や手順のこと。基本的には、画像内の物体やテキストデータを検出・分類する役割を果たします。
医療分野の画像診断や製造業の品質管理、交通分野の自動運転、セキュリティ分野の監視システムなど、さまざまな分野で活用されている技術です。
画像解析AIアルゴリズムの基本的な仕組み
はじめに大量の画像データを収集し、前処理を行います。次に、前処理された画像から、エッジやテクスチャ、色などの特徴を抽出し、AIモデルに学習させてトレーニングを実施。
トレーニングしたAIモデルの評価・検証を行い、ブラッシュアップした後に、新たな画像に対して分類・検出などのタスクを実行する仕組みです。
主要な画像解析AIアルゴリズムの種類と特徴
ロジスティック回帰(Logistic Regression)
ロジスティック回帰は、与えられたデータが特定のカテゴリに属する確率を予測するアルゴリズムです。画像解析の分野では、手書き数字の認識や簡単な物体の有無を判定するシステムに利用されています。具体的な例は、郵便番号の自動読み取りシステムなどです。
決定木(Decision Tree)
決定木は、データの特徴に基づいて一連の条件分岐を行い、最終的な分類や予測を行うアルゴリズムです。製造ラインの不良品検出システムが代表的。製品の良品・不良品を判定する画像解析システムなどに利用されています。
ランダムフォレスト(Random Forest)
ランダムフォレストは、複数の決定木を組み合わせて予測精度を向上させるアルゴリズムです。さまざまな専門家の意見をまとめて、最終的な判断を下す様子をイメージすると分かりやすいかもしれません。医療分野では、画像解析で皮膚病変の良性・悪性を分類する際に利用されています。
サポートベクターマシン(SVM)
サポートベクターマシンは、データの要素を分類するための「境界線」を見つけるアルゴリズムです。特に、2つの選択肢を用いる「2値分類」が得意です。
画像解析分野における用途は、監視カメラの顔認証システムや手書き文字のデジタル変換システムなど。高制度の分類が必要なタスクで活用されています。
クラスタリング(Clustering)
クラスタリングは、類似度によってデータをグループ分けするアルゴリズムです。1つの特徴だけでなく、複数の特徴を使用することが可能。具体的な用途は、写真ライブラリ内の類似画像をまとめる機能などです。
主成分分析(PCA)
PCAは、高次元データを低次元に圧縮し、主要な特徴を抽出するアルゴリズムです。利用例としては、顔認識システムでの特徴抽出や画像圧縮などが代表的。大量の顔画像データから特徴的な要素を抽出することが可能です。
Q学習(Q-Learning)
Q学習は、静的なデータセットに依存せず、AIが試行錯誤を繰り返しながら目的達成のための行動を自律的に学習するアルゴリズムです。ゲームのプレイヤーが経験を積むように、AIも評価(報酬)を得ることを目的に行動します。
画像解析における用途は、自律走行ロボットが障害物を避けるための視覚システムなど。ロボットが視覚情報を基にして、適切な移動経路を学習する際に利用されます。
畳み込みニューラルネットワーク(CNN)
畳み込みニューラルネットワークは、画像データから特徴を自動的に抽出し、高精度な分類や認識を行うディープラーニングモデルのアルゴリズムです。画像解析の分野では、製造ラインの不良品検出システムや医療分野の画像診断支援システムなどに幅広く利用されています。
再帰型ニューラルネットワーク(RNN)
RNNは、時系列データの処理に特化したディープラーニングモデルのアルゴリズムです。過去の情報を考慮して出力を決定する仕組みで、主に動画データの解析や、連続するフレーム間の関係性を学習する目的で利用されます。
具体的な用途は、手話の動作解析システムや連続した手書き文字の認識システムなどです。
敵対的生成ネットワーク(GAN)
敵対的生成ネットワークは、データの生成と識別を行う2つのネットワークを競わせることで、リアルなデータを生成するディープラーニングモデルのアルゴリズムです。
画像解析の分野では、低解像度画像の高解像度化や、医療分野でのシミュレーションデータ生成などに利用されます。具体的な用途は、古い写真の修復システムや、疾患のシミュレーション画像生成システムなどです。
画像解析AIアルゴリズムの選び方
画像解析AIアルゴリズムを選定する際は、開発するシステムの目的や要件に合わせて選ぶことが重要です。どんな目的を達成したいかによって、選ぶべきアルゴリズムの種類が異なります。
| 画像分類(Image Classification) | 画像が何を示しているかを判断し、カテゴリ別に分類する |
|---|---|
| 物体検出(Object Detection) | 画像のどこに何があるかを特定し、物体の位置まで把握する |
| 画像セグメンテーション(Image Segmentation) | 画像をピクセル単位で分類し、各領域が何を示しているかを特定する |
| 光学式文字認識(OCR) | 画像内の文字を認識し、テキストデータに変換する |
| 画像生成(Image Generation) | 画像を高解像度化する、またはデータ拡張のための新規画像を生成する |
| 異常検知(Anomaly Detection) | 正常なデータのパターンを定義し、製品の傷・不良箇所を検出する |
画像分類はほとんどのアルゴリズムで対応できますが、複雑なアルゴリズムほど膨大なデータ量と高性能な処理能力が必要になるため、予算に合わせて選んでみてください。
物体検出や画像セグメンテーションが目的の場合は、畳み込みニューラルネットワークが有効です。光学式文字認識を目的とする場合は再帰型ニューラルネットワーク、画像生成を目的とする場合は敵対的生成ネットワークを選ぶと良いでしょう。
異常検知を目的とする場合は、主成分分析やクラスタリング、畳み込みニューラルネットワークなどが適しています。
画像解析AIを開発・実装する際のポイント
まずはデータの品質と量を確保し、誤検知や見落としを減らせるような学習データセットを用意しましょう。学習データのラベル付け(アノテーション)が正確であればあるほど、AIモデルの精度が向上します。
リリース前の検証や運用段階では、定期的な精度評価とAIモデルの再学習を実施してください。画像解析AI開発ツールや画像解析AI開発ソリューションを利用するのも一つの手段です。
また、当メディアではシステム開発の業界・目的別におすすめの画像解析AIを紹介しています。製造業、医業、金融業など、開発システムを活用する業界・目的によって、選ぶべき画像解析AIは変わってくるもの。自社の開発システムに合った画像解析AIを導入したいと考えているSIer・AI事業者の皆様は参考にしてみてください。
画像解析AIのおすすめ3選
様々な画像解析AIのなかで、DX化実現のため大規模なシステム構築が求められる製造業、高度な解析精度が医療業界、セキュリティが重視される金融業界と3つの業界で目的に合うツールをピックアップしました。
確立したい
Bind Vision
(キヤノンITソリューションズ)

https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/cross-industry/image-integration/bindvision/brand
- 拡張性の高いプラットフォームで、用途・ライン別の分割運用、全体の統合管理が可能。カメラの増設にも柔軟に対応
- 製造ラインの状況を一画面で俯瞰し、アラート通知で異常を即時検知。Web APIでスムーズなシステム連携を実現
解析したい
Aivia
(ライカマイクロシステムズ)
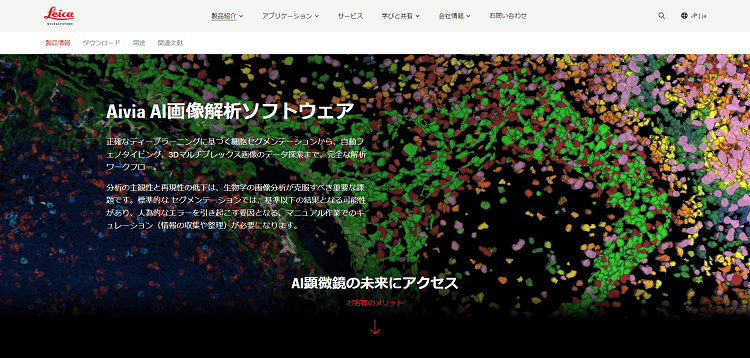
https://www.leica-microsystems.com/jp/製品紹介/画像解析システム/p/aivia/
- 生体組織に求められる2D~5Dの可視化と解析を実現。神経細胞や臓器構造の観察にも対応できる
- 45種類以上の顕微鏡画像ファイルフォーマットに対応。様々な用途の研究用データなども無駄なく活用
重視したい
Azure AI Vision
(日本マイクロソフト)

https://azure.microsoft.com/ja-jp/products/ai-services/ai-vision
- Microsoftの高度なセキュリティ基準に基づいて設計。クラウド経由の取引にも対応が可能
- 金融・保険の書類処理や自動データ抽出するOCR、オンライン本人確認機能を搭載。口座開設や本人確認業務を効率化